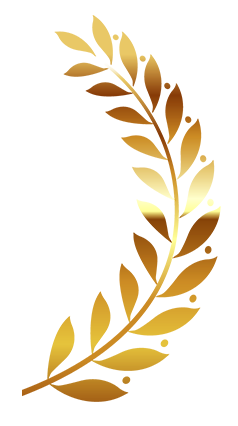手形とは
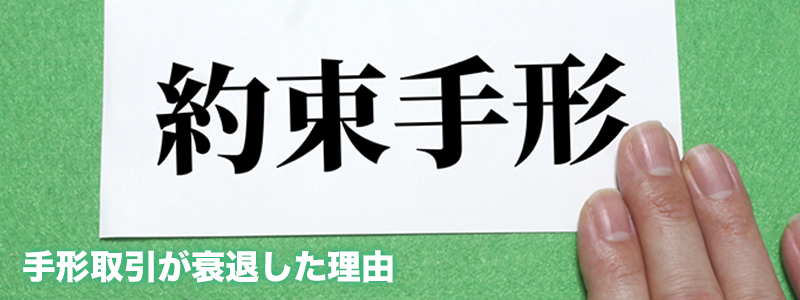
建築業界や付き合いが古い企業間取引では手形取引が今もなお多く利用されています。
一方で、決済手段としての手形(受取手形)の額面は、ピーク時である1990年度の約72兆円に比べ、2016年度で約23兆円にまで減少していることが分かっています。(財務総合政策研究所「財政金融統計月報」より)
当ページでは手形の基本的な知識をはじめ、手形が持つメリットやデメリット(リスク)、ファクタリングとの違いについて分かりやすく解説してまいります。
ビジネスにおける「手形」
様々な種類・意味合いが存在する手形ですが、ビジネスの世界における手形は「約束手形」と「為替手形」の2種類を指しています。
まず、約束手形とは、文字通りサービスの提供の対価(売買代金や業務委託報酬など)として支払われる代金を一定の期間後に支払う約束を記した証書のことです。
手元に現金が無くても商取引が可能となり、古くよりビジネスに常用されて来た経緯があります。
日本国内に於いて用いられる手形の9割以上がこの種類に該当しますので、ビジネスシーンでは「手形=約束手形」と置き換えても良いでしょう。
一方で、為替手形とは手形を発行した企業が第三者に支払いを委託する形式の手形です。
例えば、銀行に為替手形を発行すると、銀行は当該企業に代わって口座から買掛先に代金を支払います。
また、為替手形は売掛債権がある取引先等へ発行する場合もあり、この場合、為替手形を発行された取引先は、売掛債権を発行元ではなく発行元の買掛先へと支払う形となります。
手形のデメリット・リスク

以前は商取引には欠かせない存在とも言えた手形取引ですが、昨今では手形取引を拒む企業も多く、取引高は年々減少しています。
利用が減っている理由として、手形が持つ3つのデメリット・リスクが挙げられます。
倒産・債務不履行リスク
手形は一言でいうと「信用取引」であり、物的担保や保証人等を要さずに代金の支払いを猶予している状態です。
つまり、売買代金の支払いとして約束手形を受け取った場合、売主は「商品を引き渡したにもかかわらず代金が支払われていない状態」という不安定な立場に置かれます。
したがって、万が一この間(支払期日は2~3か月後が一般的)に債務者が倒産してしまうと、債権者は当該金銭の回収が難しくなってしまい、結果商品代金を丸々損してしまう恐れがあります。
現に、中小企業の倒産原因・第一位は「取引先の不渡りによる売掛金未入金」となっており、たった一つの債務不履行が次々と倒産を招くこと(いわゆる連鎖倒産・黒字倒産)も決して珍しくはないのです。
発行時にコストが掛かる
手形は課税文書となりますので、金額に応じて印紙税を納めなければなりません。
具体的には、振り出した手形の額に応じて200円から20万円の印紙を購入し、課税文書へ貼付する方法によって納税します。※印紙の金額はこちら(国税庁HP)
債権額に比べるとさほど大きな金額とは言えませんが、反復継続して振り出すとなると無視できない出費です。
さらに、支出のタイミングも不確定ですので、財務状況が不安定に陥りやすいと言えます。
詐欺リスク
手形は詐欺に用いられることが多い金融商品であり、中でも「取込詐欺(パクリ屋)」と呼ばれる手口はご存じの方も多いのではないでしょうか。
これは、商品を約束手形払いで注文し、計画的に倒産をすることで、商品のみを搾取するという詐欺手口です。
また、手形の回収を約束し手形を預けたがそのまま手形を持って消えてしまう・商取引が無いのに手形を発行させる(融通手形)といった手口も横行し、市場が混乱に陥ることも珍しくはありませんでした。
現在に至るまでに多くの企業が詐欺被害に遭っており、現代に於いてもなお一定数の被害報告がなされておりますので、これらの詐欺被害に遭わないために手形取引を避けている企業は多いと考えます。
黒字倒産とは
先ほど登場した「黒字倒産」について、少しだけ解説をしたいと思います。
これは、文字通り会社が黒字(損益計算書上は利益が出ている)なのにもかかわらず、会社が倒産してしまうことです。
サービスを提供した対価としてお金を得る場合、会計上は収益(売上)及び資産(現金預金・売掛金又は未収金等)が増えますので、一般的には売上が多ければ多いほどその会社はお金を持っていることになります。
ただし、売掛金や未収金等はあくまでも「お金を受け取れる権利」に他ならず、自由に使えるお金とは言えません。(現金や小切手等で決済された場合を除く)
つまり、帳簿上は黒字なのにも関わらず、実際の入金がなされるまで、スタッフへの賃金支払い・仕入代金の支払い・税金の納付などができない状態なのです。
「黒字なのに倒産することなんてあるの?」
と疑問に思う方も多いかもしれませんが、1つの未払いによってキャッシュフローが停滞し、遂には倒産してしまうという事例は決して珍しくはありません。
手形割引とファクタリングの違い

次は「手形割引」について学んでいきましょう。
手形割引とは、期間が到来していない手形を第三者(割引人)へ譲渡し、手数料を支払った上で現金に換える資金調達方法です。
一般的には、銀行や消費者金融等の金融機関が割引人となり、割引人は満期日までの利息及び手数料を差し引いた上で代金を支払います。(なお、手形割引を反復継続して行うには貸金業登録が必要であるため、一般的なファクタリング会社では手形割引を扱っていません。)
ファクタリングのスキームと酷似していますが、手数料やリスクについては大きな違いがあります。
手数料とリスクの違い
手形割引をする場合は「割引手数料」、ファクタリングをする際は「ファクタリング手数料」を支払わねばなりません。
割引手数料は1~5%(年率15%以内)・ファクタリング手数料は1~15%が相場であり、コスト面では手形割引の方が優れていると言えます。
ただし、手形割引の場合、振出人が倒産した又は債務不履行時の返済義務を負わねばなりませんので、リスクやデメリットも手形の方が高いと言ってよいでしょう。
一方、ファクタリングの場合は債権そのものを譲渡するため、デフォルトリスク・債務不履行のリスクは新債権者であるファクタリング会社が負います。
つまり、万が一倒産等が生じてもファクタリングには返済の義務がありません。
手形の裏書とは
手形割引は、譲渡する手形に必要事項を記入した上で金融機関に引き渡します。
これを「手形の裏書」といい、手形の裏書人は、債務者(手形の振出人)及び他の裏書人と連帯して債務を返済する責任を負います。
つまり、手形を買い取った金融機関は、経営状態悪化等によって信用が著しく低下又は債務不履行に陥った際に、裏書人に対しても請求が可能です。
したがって、手形を現金化しても、振出人が債務を履行しなかった場合、譲渡人は当該手形を再度買い戻さなければならなくなってしまいます。
取引手順の違い

手形は証券化された債権ですので、譲渡の際には当該証券を引き渡さねばなりません。
そのため、手形割引をする際は金融機関の窓口に足を運ぶ必要があり、取引も当該金融機関の営業時間内に限定されてしまいます。
一方で、ファクタリングは実体の無い権利のやり取りですので、双方の意思の合致によって権利が移転します。
つまり、何らかの書類のやり取りはもちろん、条件が整えばお互いが顔を合わせることも無く手続きは完了します。(印鑑証明書や登記簿謄本などの原本書類については後日郵送するなどで対応)
近年では、エビデンス資料はスキャンメールやスマホカメラで撮影したものでOK・事前のすり合わせは電話やLINE・リモート会議でOKといった「オンラインファクタリング」と呼ばれる方式のファクタリングサービスが増えています。
こちらは、文字通りすべてのやり取りがオンライン上で行えるサービスです。
事務所に足を運ぶ手間が無いという点に加え、それらに要する旅費交通費が必要なく、スピード面でも非常に優れています。
また、従来は事務所が遠くてファクタリングが利用できなかった・一人で仕事をしているため足を運ぶ時間がなかったといった企業にもマッチし、可能性を大きく広げた画期的なサービスと言えるのではないでしょうか。
まとめ~手形割引との違い
手形割引とファクタリングの主な違いは以下の通りです。
| 手形割引 | ファクタリング | |
|---|---|---|
| 手数料 | 1~5% | 1~15% |
| 審査時間 | 1週間程度 | 1~3日 |
| オンライン取引 | 不可 | 可 |
| 郵送取引 | 不可 | 可 |
| 取引可能時間 | 窓口営業時間 | 24時間可能 |
| 買戻請求 | 有 | 無 |
手形割引には手数料が低いという利点がありますが、取引が銀行窓口の営業時間内に限定されてしまう・手形を直接持ち込む必要があるというデメリットがあります。
そして、やはりなんと言っても債務不履行時に責任を負わねばならないという点は、企業にとっては大きなデメリット・リスクと言えるのではないでしょうか。
手形取引が日本の高度成長・経済発展を支えてきたのは間違いありませんが、現代において全ての中小企業にマッチする決済方法・資金調達方法とは言い難いのも事実です。
銀行から融資を断られてしまった・手形の裏書が不安といった方は、一度ファクタリングによる資金調達を視野に入れてみても良いかもしれません。